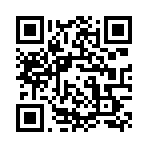2015年01月11日
山梨へ

今更ですが、明けましておめでとう御座います。
年明けてから初めてのブログアップになります。つい先日のことですが、山梨へ地元の葡萄農家仲間で一文字ロケット製枝剪定の講習に行ってきました。
今までもこの製枝剪定方法は果研や普及センター、JAなどからも教わってきましたが、どうも理解し切れていませんでした。そもそもこちらに教える側も完全に理解していなかった方もいると思います。そのくらい奴白さん直々に教わると違っていました。そもそもが良品を作り、10人中8人くらいが同じように剪定出来るということですから、短梢栽培のように作業の単純化を目指すのとは対局にある仕立て方です。ある意味、剪定や夏場の管理などはルールに従ってやれば問題無く出来るという感じです。
それともう一つ、この仕立て方はやはり自然系のX字製枝を分かりやすく具現化したようなものなので、目指す方向が短梢栽培と違いますね。
座学と実技の両方で実際に教えて貰って剪定すると理解したつもりでも理解していなかった点が多々あり、こんな為に成る講習は他には無いと心底思いましたね。今回誘われなかったら中途半端なロケット製枝をしているところでしたよ。
この仕立ては単純明快ですが、おかげで自然系の仕立てを人に説明できるようになったような気がします。感覚ではなく、根拠を持って切る切らないの説明です。
今回のことで全てが上手くいくわけではありませんが、知識の幅を広げるのとスキルアップですね。こうやって諸先輩方のお話を聞いて自分なりに消化して今後に繋げていけたらと思いますね。思いますじゃなくて繋げていくですね。
詳しくはホームページにて♪
2013年08月11日
視察に行ってきました

先日、山梨の植原葡萄研究所さんへ葡萄仲間三人で伺いました。
それぞれ葡萄専業農家でそれなりに経験を積んでいて、葡萄に対して真剣に取り組んでいる者同士ということで移動の車中での会話がマニアック且つ、専門的でたぶん高度な内容?で濃い会話を楽しめました。
植原さんのところではそれぞれの品種についての説明ばかりでなく栽培についてや品種特性、系統などとても突っ込んだ内容で話をしながら圃場見学と葡萄の試食もさせて戴きました。
副所長の剛さんには本当にお世話になりました。いつもの事ながら新品種というのはワクワクします。
今回はそれぞれマイスターを自認する3人と本当の専門家植原さんの4人でしたから濃い内容でしたよ。
中身の濃い充実した視察でした。
その後は山梨のB級グルメでランチしてワイナリー巡りをしてきました。ワイナリーでも風間さんから話を伺ったりして突然の訪問にもかかわらず、親切に接して頂き本当に感謝ですね。
縁って大切だなぁとつくづく思った一日でもありました。
詳しくはホームページにて♪
2011年10月17日
試してみたいこと

先日、長野市周辺の若手ぶどう農家の集まりで果樹試験場での品種検討会に参加してきました。詳細はうら日記にも書きましたが、その中で私が注目したい技術でスマートヨーガとジョイント方式ですね。
ジョイントはまだ未知な部分がありますが試してみたいです。効果の程も解明されていないことだらけですが・・・
スマートヨーガは醸造用で結果が出ている技術なので生食用でも通用すると思います。
特に着色難の赤系品種に有効だという結果が出ています。
南側から必ず陽が差し込むのと、収量は減るかもしれないが適正着果量になるので自ずと着色向上と粒張りがよくなる。そして味も良くなる。こういう利点から黒系や白系品種にも有効だと思われるという考察らしいです。
白系は熟度に注意ですが。
新品種についても試食したり、栽培状況の確認などで実際に目で見てきたので、こらからの経営に取り入れる品種について大変参考になりました。
来週は果樹研究会の研修もあります。
この時期は勉強する機会が沢山あって楽しいです。
詳しくはホームページにて♪
2011年10月13日
視察旅行兼家族旅行

家族旅行を兼ねて新潟と山形のワイナリー視察と苗木屋さん訪問を行ってきました。
ここからはうら日記と被る内容ですが、ちょっと追記もしつつブログアップです。
上が高畠ワイナリーで見た樹。下がタケダワイナリーで見た樹。

どちらも剪定方法こそ若干の違いはあるが、品種の違いと圃場の違い程度にしか分からない写真かもしれません。
違いは高畠地区と上山地区という隣り合ってはいるものの、蔵王連峰の火山灰土が残る上山と同じ火山灰土でもゼオライトが多く含んでいる高畠地区の違いもさることながら、ちょっとした気候の違いで両地区とも葡萄畑全体に言えることで3309と無毛テレキに大きく分かれるということです。
高畠地区はほぼ3309。対して上山はほぼ無毛テレキと。
苗木屋さんとしては土地柄も左右すると言います。この辺りでは5BBでは難しいというか良果を穫るためには3309と無毛テレキという選択肢になるのだそうです。あとはグロワールが適地?という見解です。
そういう話のもと、樹を見れば台が勝っていたり、台がやや負けていたりと特性も垣間見れて興味深いですね。3309は台負けがしにくい品種で無毛テレキは台負けする品種です。そうして見ると樹の感じが違って見えます。ぱっと見で樹幹に一番の違いが分かるかと思います。
更に圃場の土も同じ火山灰土とは思えない違い。どちらかというとタケダワイナリーの方が根が深く張っている印象。大して高畠ワイナリーは台木の特性から深くと言うより横に広がっている印象。台木の特性から無毛テレキは太く深くある特性、3309は中深だけど広く広がる特性。
こういう違いもさることながら、苗木屋の話では高畠地区では3309の方が向いているとのこと。そして、上山地区は無毛テレキの方が向いているそうです。
品種特性もありますが、こういう台の選び方一つがワインの味にも表れるのでは?と思います。やはり自根樹の方が繊細さが出てきますが、力強さでは台に接ぎ木した方があります。また、台の選び方一つで力強さも変わってきます。
生食用を栽培する上では棚上での作業技術を見がちですが、大事なのは根と土、台木だと思います。それだけでも随分違う果実が産まれます。
これは醸造用でも言えるのでは無いでしょうか?テロワールの概念が強い醸造用の方が土と根、台木を第一に考える向きが強いですね。
醸造用も生食用も葡萄は葡萄ですから根本は一緒です。考え方の違いはありますが・・・
詳しくはホームページにて♪