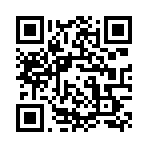2013年02月16日
今はこういうときでも

剪定が遅れているために、こういう天候でも畑に出て剪定です。
今年は大幅に遅れているためにこういう天候でも休めなくなっています。年が変わる前にやっていればこういうことは無いのですけどね。
どうしても1,2月は雪が降って畑に出られないことが多いために雪が降る11、12月で剪定をある程度終わらせるのが理想なんです。ですが、この現状・・・
こういうときはサクサクと動けるように落とす枝だけに的を絞って、なるべく身体を動かす作業にします。そうすると身体がポカポカしてきますから。
いつものように考えながら「あーでもない。こうでもない。」と色々と錯綜しながらですと身体が冷え切ってしまいますからね。
詳しくはホームページにて♪
2013年02月11日
ようやく一つが終わりを

今日は朝から吹雪いている坂城です。天候に左右されるのは冬の農閑期だから仕方ないですね。
昨日は本当に良い天気で剪定日和でした。剪定もようやくメイン圃場の方が残り2反歩と終わりが見えてきたのでホッとしています。それでも他にも畑はあるので剪定そのものは終わりませんが・・・
写真の樹は40年生の巨峰に高接ぎしたシャインマスカットです。この樹は後数年で伐採予定ですが、予想以上に良いものが採れるので伐採縮小を躊躇して現状維持よりもやや拡大です。ややいびつな樹形ですが、高接ぎということでどうしても勢いのある強い芽が出てしまい、混んできてこのようにいびつになってしまいます。それでも根が勝っているのでまだまだ拡大の余地はあります。
このように剪定も短梢と中梢とこういういびつな中梢と長梢など色々とやっているので時間はかかりますね。まだまだ終わりは先のようです。
詳しくはホームページにて♪
2013年02月08日
まだ終わる気配無し

今年は雪で剪定が遅れることがしばしばあって思うように進まないのが現状で悩みの種です。
早く終わらせて別の作業へ移りたいところですが、まだまだ終わる気配の見せない進行状況で剪定しています。
遅れる原因にもなっている中梢仕立てが多いのが難点ですね。
樹勢を見て落とす枝を見極めてから切っていくので時間はかかります。短梢仕立てだと一直線に切っていくだけですので機械的に作業を進められ早く終わらせることが出来ます。
一部では短梢を導入していますが、殆どの樹が写真の様に中梢なので当園の剪定は時間がかかります。
ですが、品質を追求するとより自然な樹形の方へ軍配が上がるので中梢から短梢へとシフトしきれないのが現状です。
詳しくはホームページにて♪
2013年02月01日
作業再開

先週は不覚にもインフルエンザに感染してしまい作業が全く出来ない一週間でした。
インフルエンザに感染するのはかれこれ10数年ぶりくらいでここのところ風邪すらもひかない健康体なのに、ここにきて・・・という感じです。
2,3日前から作業を再開して、今では普通に剪定しています。ここ数日は天気もよく雪解けが進んで、畑にも殆ど雪が残っていない状況ですので剪定も捗ります。
今やっているエリアは苗木が所々に入っているので、その苗木を優先した剪定です。混み入った箇所の剪定よりは、どれを優先するか?というのがはっきりしているので切り縮めるの方の樹を容赦なく切っていけばいいので樹形を気にしなくていいので簡単です。
毎回こういった剪定だけだと流れとか樹形とか気にしなくて良いので簡単ですが、まだまだ色々考えなければ剪定出来ない樹が多いので時間はかかりそうです。
詳しくはホームページにて♪
2013年01月24日
WINE FORUM in NAGANOキックオフイベント

一昨日ですが県の主催する「WINE FORUM in NAGANO」に参加してきました。
簡単に言うと長野県は「信州ワインバレー構想」というプロジェクトで「NAGANO WINE」を世界に誇れるブランドにしていこうというものです。
知事の決意からもこのイベントの重要さが伺えますし、何より本気でこのプロジェクトを推進していこうという気概が感じられました。
ディスカッションでは玉村豊男氏が司会進行役で阿部知事、井筒の塚原社長にワイナート編集長の小松さんと蒼々たる顔ぶれで非常に興味深いお話しが聞けました。
私もこの流れに乗り遅れないように坂城町ワイナリー形成事業を出来る限りバックアップし、自らもNAGANO WINEのなかでもブランド化を図り、キュヴェナルサワを作れるように栽培技術を磨いていこうと思います。
詳しくはホームページにて♪
2013年01月20日
ワイヤ張り

14日に降った雪は膝まで積もりましたが、10〜20センチほどにまで溶けて畑の中を歩けるようになりました。
そんな中、資材の業者「新洋」さんがこちらへ来られるとのことでレクチャーを受けながらワイヤをとりあえず1列だけですが張りました。
この資材はコストパフォーマンスに優れていて作業性もよく、このまま普通の葡萄棚に使えそうなものまであったので次回は生食の方の棚にも導入を検討します。
一方、もう一つの圃場での資材は別の会社ですが、こちらは残念なことに作業性が少々悪いのが気になります。今回張ったワイヤにしても1〜2人で可能ですが、もう一つの圃場は1〜2人では難航しそうな感じなので少々気が重いです。
今回張ったワイヤですが、雪解けを待って続きを行うことになりそうです。ようやくvineyardらしさが出てきています。ワクワクしますね。
詳しくはホームページにて♪
2013年01月13日
アンカー埋め替え

葡萄棚の古くなったアンカーを交換する作業をしました。
以前のアンカーは開園した当初に埋めたもので、当時は大きな石に針金を縛り付けただけの簡素なものでした。当然、針金は腐食して錆び付いて切れたりと劣化しています。
そういった過去の遺物を何年かかけて行っていますが、まだ全て交換出来ていません。アンカーだけで何個埋まっているのか数えたことはないですがおそらく100コはあるかと思います。当園のように一箇所に圃場が集まっている場合は周囲全てにアンカーが埋まっているばかりでなく、中にも補強用に埋まっているので無数にアンカーがあります。
それら全てのおかげで幾度となく来る台風や豪雪に見舞われても耐えることが出来たのだと思います。これからも自然災害に耐えて貰う為にもこうした棚の補修は毎年行っていきます。
詳しくはホームページにて♪
2013年01月09日
巨峰の整理

当園では近年、シャインマスカットとナガノパープルへの大幅改植に伴って巨峰の整理が行われています。
剪定も殆どがあちこちに植えられている樹を優先的にしていくので巨峰はどんどん勢力を縮小しています。こういった剪定は樹形は関係無く、邪魔な枝を取り除いていくという剪定方法で、簡単っぽいですが、案外考えることが多いので時間がかかります。
早くこの作業から脱却して剪定にらしい剪定にしていきたいものです。それにはあと2,3年はかかりそうです。
詳しくはホームページにて♪
2013年01月02日
新年明けましておめでとう御座います

明けましておめでとう御座います。
今年も宜しくお願いします。
新年の初詣には地元の坂城神社にて今年の良作と家族が幸せに健康で過ごせますようにと祈ってきました。
今年は樹齢40年にもなる巨峰の樹が4本ある一枚の小さい畑を改植してナガノパープル単一へ生まれ変わる畑もありますので収量的には減ります。ですが、大幅に増えるシャインマスカットとクイーンニーナ、ナガノパープルに対処するための体制作りと申しますか技術を確立しなければならないと年でもあります。
色々と忙しくなりそうですが、夢である荒廃農地を開墾して新たな景観作りは町のワイナリー形成事業で引き継いで貰ってこちらもいよいよ軌道にのります。
そして、私個人の夢は軌道修正というかキュヴェを作るべくこぢんまりとやっていきます。
どちらにしてもワイナリーはそう遠くない将来に坂城町に誕生します。その時にキュヴェをリリース出来るように更なる拡張もしていきます。
今年も上ノ原果樹園を宜しくお願いします。
詳しくはホームページにて♪
2012年12月29日
仮伏せ

本日、新たに苗木が到着しました。
時期が時期なだけに定植は翌春に見送って、今回は土中に埋める仮伏せにして眠らせることにしました。
翌年の生育を考えれば秋植えか初冬の冬に植える方が望ましいのですが、すでに年末で土は凍っていて寒波も来ている状況を考えれば仮植え(仮伏せ)が望ましいですね。
今回は予てから親交のある苗木屋さんから秘密の苗木が届いたので大事にしたいです。今のことろは自家増殖はせずに大事に育てていきます。
3年後が楽しみです。
詳しくはホームページにて♪
2012年12月23日
垣根作り

醸造用葡萄の畑に隅柱を設置しました。
町のワイナリー形成事業で第一圃場にはこのような形式の垣根となります。第二は別の業者から資材を買うので第一と違う形式です。
どれも垣根には違いないですが、業者によって考え方が違うのでどれが良いのか分かりませんが、個人的にはなるべく安く上がる方法がベターだと考えています。
山梨の著名な栽培家の先生から仕立て方で葡萄の善し悪しが決まるものではないと教えて頂きました。
私もそう考えますね。
仕立て方よりも時期の見極めとその時期に適切に処置しているかだと思っています。
早く自分の栽培理論を科学的かつ論理的にまとめたいものです。
詳しくはホームページにて♪
2012年12月15日
今年の冬は

今年は昨年よりも早くに寒波の襲来があり、冬囲いが追いつきませんでした。
葡萄は−20℃までは耐えられる寒さに強い植物なのですが、それも徐々に寒くなっていっての話です。それが一気にー10℃という寒波がきて若木は心配です。
徐々に気温が下がっていけば樹もそれなりに耐性を整えて寒さに耐えられるように、人間で言えば肉体改造みたいなことをしていきます。
それが一気に下がると耐性が出来上がっていないものですから最悪の場合は翌年には芽も吹かずに枯れてしまうこともあります。
特に若木は藁で耐寒しておくのが理想です。冬の寒さには耐えられても、春先の水あげの始まった時にくる霜でやられてしまうことがあるからです。
樹自体も糖によってある程度の凍害には耐えられるように自らの身体を作り替えているので、ある程度年を重ねた樹は冬囲いをしません。若木だけは心配なのでやっていますが、今年のように早い時期の寒波は勘弁願いたいですね。
詳しくはホームページにて♪
2012年12月06日
果研の剪定講習会

長野県果樹研究会ぶどう部会の剪定講習会に行ってきました。
毎度の事ながら剪定技術というのはセオリーはあってもその通りにならない事ばかりです。
試験場の先生に質問したり、部会長の飯塚さんに疑問点を聞いたりしたのですが、自分の中で理解度というのは変わってきたのが実感しました。昨年一昨年では理解出来なかった点もありましたしね。
剪定は寒い中に作業するのであまり好きではないですが、これこそ腕の見せ所という作業かもしれませんね。
この作業で翌年の出来も随分と変わってきますし、見た目の技術ではなく隠れた技術という意味では渋いテクニックです。
まだまだ精進あるのみです。
2012年12月04日
巨峰の伐採に藁カット

剪定の前に取りかかった「巨峰の伐採」作業も今日で終焉を迎えました。
これで心置きなく、この畑は巨峰畑よりナガノパープル畑へと生まれ変わります。
苗木は既に用意してあって、今度苗木はSt.ジョージの台木にいであるのでやや晩生気味だけど、耐寒性と耐乾性ともに強いのでこの雨量が極端に少ない当地にはうってつけで期待しています。
午後は畑を移動して今度は藁カッターで藁をカットする作業。昨年まで一人でやっていたので2〜3日かかっていましたが、今年は研修生と共にやってたったの半日で。
や1+1=2にはならない農作業。3にもなるし4にもなったりする。この調子で剪定も早く終わらせたいものです。
詳しくはホームページにて♪
2012年12月02日
今はこんな感じです

この畑は今まで巨峰の畑でしたが、今度はナガノパープルに改植する予定なので今は伐採しています。
この伐採するというのは気持ちの良いものですが、どこか悲しい気分になります。やはり今まで働いてくれたという感謝の気持ちがあるからですが、それにしてもこの畑の今日は樹齢40年になろうかというものなので随分と働いてくれた樹でもあるのです。
今年は最後ということで随分と無理させてしまいましたが、それでも最後の力を振り絞ってくれたのか、他の畑に比べて抜きんでた粒の大きさで最後の最後で良いものが採れました。
実は今まで良いときと悪いときのムラがある葡萄が採れた畑でもあるのです。ですが、当園では一番標高が低いので最も早く熟期がきてくれたので8月中から収穫が出来たのでそれはそれで良い畑でもありました。
今度はナガノパープルに生まれ変わって良質なものが採れることを願っています。
詳しくはホームページにて♪
2012年11月24日
初日完売です

随分と日が経ってしまいましたが「巨峰ヌーヴォー」が今期製造分が解禁初日で完売しました。
次回は2月予定のスパークリングです。ちょっと炭酸がきついですが、口に突き刺さるような刺激がのどごしの良さを演出していると思います。
関係者として初日完売は嬉しい限りですね。
まだまだファーストヴィンテージは先の話ですが、それまでに巨峰ヌーヴォーやスパークリングで坂城町にワイン文化が育つことを期待します。
だけどその前に当園のファーストヴィンテージが秘密裏にリリースされるかもしれないですがね・・・
詳しくはホームページにて♪
2012年11月17日
本家ヌーヴォー解禁に対抗?して解禁!

今年から我が町坂城町で待望のワイナリー形成事業がスタートして、ワイン人口を増やすために万人に受け入れやすいワインをリリースしようということになって、ついに坂城産巨峰ヌーヴォーが解禁になりました。
今日は「さかき地場産直売所あいさい」でねずみ大根祭りの開会式にあわせて巨峰ヌーヴォーの試飲販売も併せて行われました。
解禁初日というこもあり飛ぶよう売れ、売り切れ必至となるのは間違いないでしょう。肝心の味はヌーヴォーらしい若々しさに溢れ、万人向けの甘口となっています。フルボディなど好きな方には物足りないことと思います。個人的にも少々物足りなさはありますが、5年後にリリース予定のボルドータイプのワインの為にワイン人口の裾野を広げるのに一役買うのではないでしょうか。
ただ、一点残念な点が・・・ワイナリー形成事業の言い出しっぺという立場で言わせて貰うと、千曲川ワインバレー構想の一翼を担うのであれば、やはり構想の中に入っているワイナリーに委託するのが、よりワインバレー構想とリンクするのではないでしょうか?
こんなところで辛いこと言っても始まりませんが、関係者としては少々思うところがあります。
今後のプランとしてヨーロッパのワイン産地と姉妹都市提携を進言していますので、これを推進してもらい、人的交流や文化交流など行って坂城町がワイン産地として発展していくように微力ながら一栽培者として寄与していくつもりです。
詳しくはホームページにて♪
2012年11月14日
画像はないですが
ここ最近は時間が比較的あるので研修生と一緒に視察に行っています。
先日は東御市の葡萄仲間のカネツ観光農園まで。今日は千曲市の葡萄仲間で普段から親交のある北澤ぶどう園まで。
両園とも方向性や考え方、経営方針に地域も違うので勉強になりましたね。
ただ、それぞれ特色ある栽培で研修生にとっても見るものが真新しく写ったのではないかと思います。ホームだけ見ているとどうしても固執した考え方になってしまうのと偏ってしまうので。
今度は山形や山梨も候補に考えています。
やはり安芸津や岡山には一度は訪れたいですね。短梢栽培の本場である岡山や、数々の品種を生み出している国の機関である安芸津試験場というのは一見の価値があると思います。
冬の期間は畑よりも座学も必要ですが、今年は出来るだけ見聞を広げるために外へ行こうと思っています。
詳しくはホームページにて♪

先日は東御市の葡萄仲間のカネツ観光農園まで。今日は千曲市の葡萄仲間で普段から親交のある北澤ぶどう園まで。
両園とも方向性や考え方、経営方針に地域も違うので勉強になりましたね。
ただ、それぞれ特色ある栽培で研修生にとっても見るものが真新しく写ったのではないかと思います。ホームだけ見ているとどうしても固執した考え方になってしまうのと偏ってしまうので。
今度は山形や山梨も候補に考えています。
やはり安芸津や岡山には一度は訪れたいですね。短梢栽培の本場である岡山や、数々の品種を生み出している国の機関である安芸津試験場というのは一見の価値があると思います。
冬の期間は畑よりも座学も必要ですが、今年は出来るだけ見聞を広げるために外へ行こうと思っています。
詳しくはホームページにて♪
2012年11月07日
そろそろ元肥
腰痛は相変わらずで変な格好で歩いています・・・
11月に入ってそろそろ元肥のレシピでも考えないといけない時期です。礼肥は9月下旬から10月いっぱい位を目安にまだまだ葉が青々としている段階に「一年間有り難う」という意味合いを込めて元肥の3割程度を目安に施肥。
やらなくてもやっても良いという位置づけですが、目安は葉が早くに黄色に変わって窒素が欠乏している樹を中心に施肥するのがいいと言われています。
ですが、ウチではそれだけでなく疲れ?ているような樹も対象にしています。
疲れているのは感覚的にですね。
葡萄の樹は11月下旬まではまだまだ養分を土中より吸い上げているので礼肥で翌年までの養分を補います。礼肥によって蓄えられた養分で葡萄は翌年の展葉8枚程度まで成長します。その次は元肥によって出来た土中の養分を吸い上げて肥大期まで乗り切って、追肥でその後の着色と肥大と味を作り上げていきます。このリレーが上手くいって空白期のないようにするのがポイントですね。
元肥と礼肥は一緒でも良いかもしれないですが、そこは葡萄の樹を見て判断ですね。
礼肥は疲れきってお腹が空いた樹にご飯をあげる感じです。
当園では元肥には毎年恒例のバットグアノに幾種類かの肥料をブレンドして施肥して、仕上げに堆肥と稲藁のフルコースで締めます。
幾種類かの肥料というのは足りない養分を補うのと、今年の葡萄の出来で足りない養分とか足りていた又は多すぎたとか判断してブレンドするレシピを考えますので毎年ちょっとずつ違います。
今年は・・・肥料を若干少なくする予定です。
詳しくはホームページにて♪
2012年11月03日
ようやく更新

先日のことですが果樹研究会ぶどう部会の品種検討会に参加してきました。
催しそのものは数日前でしたが、1週間〜10日程?前から腰を痛めてというか再発でへっぴり腰で日常動作が満足にできないような状態でしたのでPCからも遠ざかっていました。
医者にも言われたのですが疲れがたまっていてそれが爆発したのでしょうと。納得のいく診断でした。葡萄が10月31日で収穫終わりでしたが、その数日前より緊張の糸が切れたかのように葡萄をちょっとずつちょっとずつ小出しで休み休みでしたので疲れがどっと出て風邪を拗らせたりと散々でした。
それでも勉強はしないといけないので検討会には参加してきました。
やはり注目はクイーンニーナ。当園も積極的に導入して、シナノスマイルから品種更新を考えているほどです。それでも各JAでは積極的に導入するつもりが無いのか農家ほど熱が入っていないので温度差がありました。それでも当園が所属しているJAちくまはシナノスマイルからの切り替えを今度の総会から提案していくと言っていますのでJAちくまはクイーンニーナが増えていくことでしょう。
待望の赤系品種ということもありますが、着色しやすく、病気にも強く、何より作りやすいです。皮ごと食べられないというのがネックですがそれを補ってあまりある味です。この美味しさはかなりのアドバンテージでは無いでしょうか。
来年以降は当園でもクイーンニーナはかなりの面積を占有することになると思いますので、来期は本格的に販売していきます。
詳しくはホームページにて♪